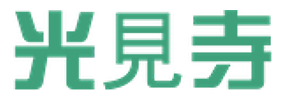もっと知る 境内紹介
-
山門
お寺の象徴として、光見寺の入口にそびえる山門。堂々と掲げられた寺名は迷わずお越しになるための目印となり、訪れた方を温かく迎え入れます。長い歴史の中で、門をくぐる皆様を静かに見守り続けています。 -
本堂
どなたでも自由にお線香をあげられるよう、本堂の前にお線香やライター、供花をご用意しています。ご先祖様や大切な方へ思いを馳せ、心穏やかに過ごしていただけるよう願ってのことです。住職の不在時は本堂を閉め、安全のためライターなどもしまっておりますが、ライトアップされた御本尊阿弥陀仏を外から拝んでいただくことは可能です。いつでもお気軽にお参りください。
また、本堂と客殿にはエアコンを設置しており、冷暖房を完備しております。椅子のご用意もございまして、ご焼香は立礼焼香(立ったままでのご焼香)となります。 -
御本尊阿弥陀仏(阿弥陀如来)
阿弥陀如来(あみだにょらい)は、「あみださま」とも呼ばれ、無限の光と命を象徴し、人々を救ってくださる仏さまです。西の彼方にある「極楽浄土」という安らぎの世界の主で、すべての人をその世界へ導いてくれると信じられています。「南無阿弥陀仏」の念仏とともに多くの人々に親しまれています。念仏を称える人は皆、死後、極楽浄土の蓮の中に生まれ変わると言われています。
また、向かって右(阿弥陀如来の左)には、蓮台を持ち慈悲を象徴する「観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)」。向かって左(阿弥陀如来の右)には、合掌し智慧を象徴する「勢至菩薩(せいしぼさつ)」が配されています。この三体の尊い仏さまは、あわせて「阿弥陀三尊(あみださんぞん)」と呼ばれています。 -
「南無阿弥陀仏」の意味
「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」は、仏さまの名前を称える言葉で、「阿弥陀仏にすべてをおまかせします」「どうかお救いください」という願いと感謝の気持ちが込められています。「南無(なむ)」はサンスクリット語で、「帰依する」「身をまかせる」という意味です。「阿弥陀仏」は、無限の光と命を持つ仏さま、阿弥陀如来を指します。 -
六地蔵
六地蔵(ろくじぞう)とは、六体の地蔵菩薩を指し、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天)の世界で苦しむ人々を救済するために祀られた仏さまです。仏教では、人は死後、六道を輪廻転生するとされ、それぞれの世界で異なる苦しみを受けると考えられています。六地蔵は、その苦しみを和らげ、悟りへと導く役割を担っています。そのため、死者の供養だけでなく、生きる人々の厄除けや安全を祈る対象としても信仰されています。 -
薬師如来像
元禄11年(1698年)3月12日に建立され、願主は長森吉兵衛、大工は冨田五左衛と棟札に明記されています。堂の正面には「国神」と刻まれた額が掲げられています。
薬師堂の本尊は高さ一尺一寸の薬師如来で、向かって右(薬師如来の左)に日光菩薩(にっこうぼさつ)、向かって左(薬師如来の右)に月光菩薩(がっこうぼさつ)が安置されています。薬師如来は、古くから病気や苦しみを和らげる仏として深く信仰されてきました。この尊い仏さまを中心に、両脇に仕える日光菩薩と月光菩薩を加えた三体は、あわせて「薬師三尊(やくしさんぞん)」と呼ばれています。
また薬師如来の足元には、甲冑をまとった十二神将が寄り添い、その世界と信仰する人々をしっかりと守っています。彼らは、仏の誓願を支え、人々を病や災いから救うために力を尽くす守りの神将です。 -
地蔵菩薩像
地蔵菩薩(じぞうぼさつ)は、「お地蔵さま」として親しまれている、慈悲深い仏さまです。特に子どもや旅人、そして亡くなった人を守り、苦しんでいる人を助ける存在とされています。地獄や困っている世界にも自ら出向いて、人々を救ってくれると言われています。 -
永代供養墓
永代供養墓は、お墓の継承や管理が難しい方のために設けられた供養の場です。時宗の教えに基づき、住職が日々供養し、ご先祖様をお守りします。
故人様を偲ぶ場を大切にしており、どなたでも気軽にお参りできる個別の供養スペースを備えている点が特徴です。お一人でも、ご夫婦でも、ご家族でも、安心してお参りください。
「子どもに負担をかけたくない」「お墓についてどうしたらいいかわからない」といった生前のご相談にも対応します。少しでもお困りの方は、気兼ねなくご相談ください。
※永代供養墓とは別に、納骨壇もご用意しております。 -
結縁交名帳(附阿弥陀如来一軀)
指定区分:市指定文化財(有形民俗文化財)
指定年月日:昭和51年(1976年)6月28日
所在地:樋口地内
管理:光見寺
時期:江戸時代
大きさ:縦12cm、横34cm
員数:1巻
この古文書は、和紙を横長に二つ折りし、横とじで6枚綴られた1巻で、表紙には「宝永元年甲申六月吉日大根田村本願念西」と記されています。昭和48年3月10日に当寺所蔵の阿弥陀如来立像の胎内から発見されました。
内容は、祈る人々の名が記された連名簿のようなもので、中世の女性たちが仏菩薩に衆生の救済と成仏を願った記録とされています。光見寺は西向山阿弥陀院と称する時宗の寺院で、かつて朱印地五石を賜っていました。この貴重な文書は、現在も光見寺が所蔵しています。